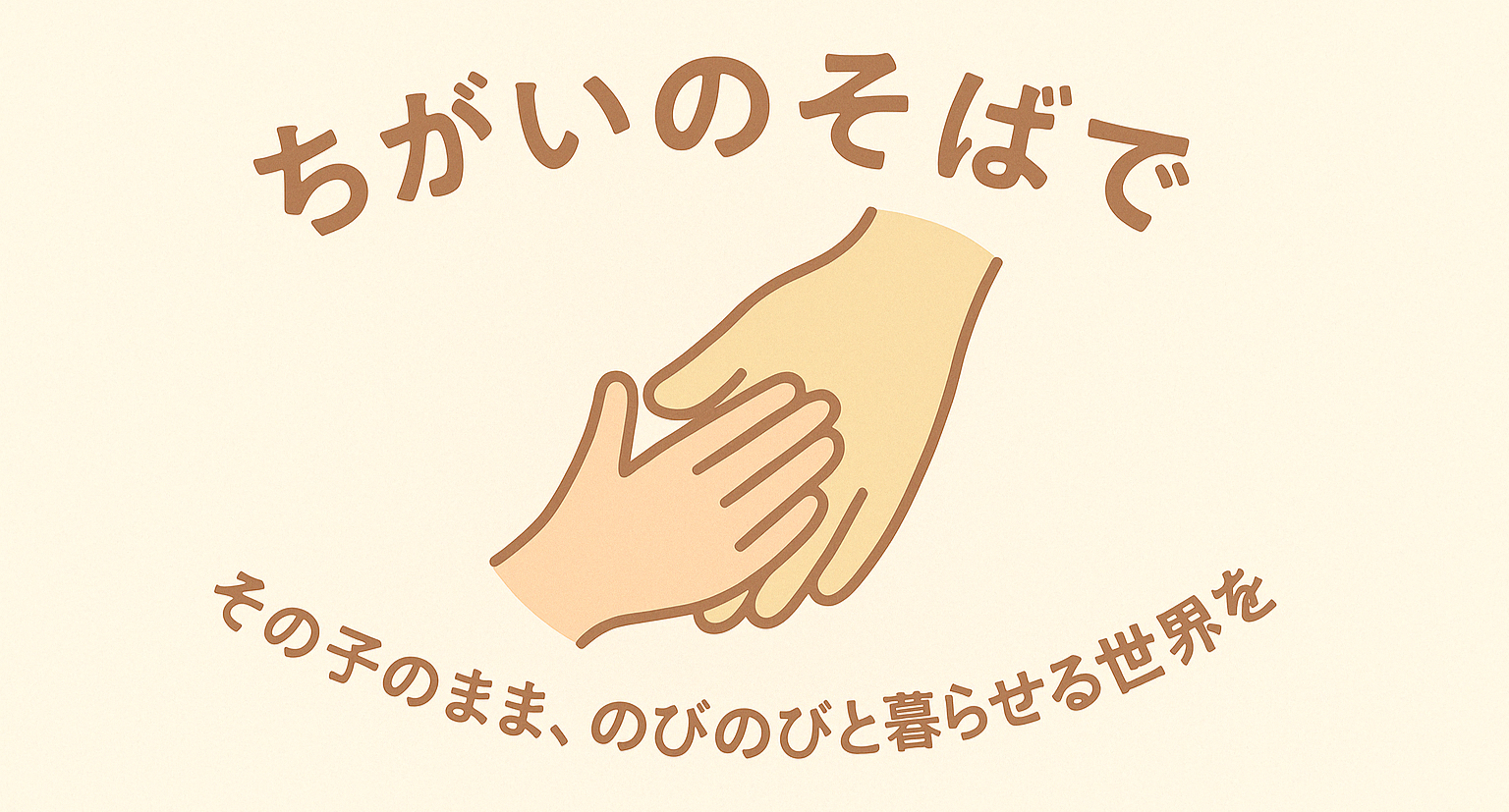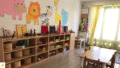新しい療育施設との出会い
療育を始めて1年ほど経ったころ、通っていた施設が一時休業することになり、
紹介を受けて新しい療育施設へ通うことになりました。
そこではこれまでのような1対1の個別療育に加えて、
4〜5人で行うグループ療育も用意されていました。
「集団行動が苦手な息子には必要かもしれない」
そう思い、週に1回ずつ、個別とグループの両方に通うことにしました。
マジックミラー越しに見た息子の姿
この施設は、親が送迎をし、マジックミラー越しに療育の様子を見守れる仕組みでした。
子どもの様子を観察し、気づいたことをメモに取り、
療育後に先生と一緒に「どうだったか」「今後どうしたいか」を話し合うスタイル。
これまでは月に一度しか様子を見ていなかったので、
息子の姿を間近で見られるようになったのはとても貴重な経験でした。
今振り返れば、息子の特性をより深く理解するために必要な時間だったと思います。
でも当時の私は、在宅勤務とはいえフルタイムで仕事をしながら週2回の療育に通う日々に、
「もう続けられないかも」と何度も思っていました。
個別療育で感じた焦り
年長になった息子は、個別療育の中で
ホワイトボードに書かれた文字を紙に書き写す練習など、
小学校を見据えた課題に取り組むようになりました。
「ちゃんとできるだろうか…」
そんな不安が日に日に募り、仕事が忙しい日に息子が集中しないと、
「忙しい中で通ってるのに、ちゃんと練習してよ!」と
つい怒ってしまうこともありました。
あの頃の私は、
「ここでしっかり練習しておけば小学校でもうまくやれるはず」
と、焦りながら息子に“頑張らせよう”としていたのだと思います。
けれど、以前のように明確な成果が見えるわけではなく、
「このまま続けて意味があるのだろうか」と迷いながらの日々でした。
グループ療育での挑戦と葛藤
グループ療育では、年中〜年長の子どもたち4〜5人が集まり、
本の読み聞かせや工作、ゲームなどを通して「みんなと一緒に取り組む」練習をしていました。
初回こそ緊張からか息子も落ち着いて参加できていましたが、
回を重ねるうちに、席を立ったり、集中できずに寝転がったりする姿も増えました。
そのたびに私は、
「このままでは小学校に行けないのでは…」と不安になり、
帰りの車の中でつい強く言ってしまいました。
「みんなと同じことをしないと小学校には行けないんだよ!」
本当は分かっていたんです。
息子に怒っても意味がないことを。
でも“普通にできるようになってほしい”という気持ちが強すぎて、
焦りや不安を息子にぶつけてしまう自分がいました。
つながりが支えになった
グループ療育は、マジックミラー越しに親が子どもたちを見るため、
自然とママ同士の交流が生まれました。
発達特性のある子の「あるある」を共有しながら共感し合い、
「どう支えていけばいいんだろう」と一緒に悩み、励まし合う時間。
同じ立場だからこそ分かり合えるそのつながりは、
今でも連絡を取り合うほど、私にとってかけがえのない仲間になりました。
療育を通して見えたもの
療育を振り返ると、たくさんの良いことがありました。
- 息子が友達と関わるきっかけを得られたこと
- 息子の特性を具体的に理解できるようになったこと
- 同じ悩みを共有できる仲間に出会えたこと
でも、同時に気づいたこともあります。
あの頃の私は、療育に“もっと多く”を求めすぎていたのかもしれません。
療育を続ければ集団行動ができるようになるはず
相手の気持ちを理解できるようになるはず
訓練で「普通の子」に近づけるかもしれない
そんな期待をどこかで抱いていました。
でも今思えば、それは“発達障害をまだ受け入れきれていなかった私”の気持ちだったのだと思います。
「普通になれば、苦労せずにすむ」
「みんなと同じように過ごせれば、楽しく学校に通える」
そんな思いが、私を焦らせ、息子を追い詰めてしまっていたのかもしれません。
もしあの頃に戻れるなら――
週2回ではなく隔週や月1回のペースで無理なく通い、
「ちゃんとしなさい」ではなく
「こういうところが苦手みたいだね」と一緒に考える時間にしたかったと思います。
いまの気持ち
療育を通して得たのは、
「普通にすること」ではなく、
「その子らしく生きるための環境をどう整えるかを考えることの大切さを理解すること」でした。
息子の特性を受け止め、寄り添いながら支えること。
それこそが、私にとって本当の意味での“動いてみたこと”だったのかもしれません。