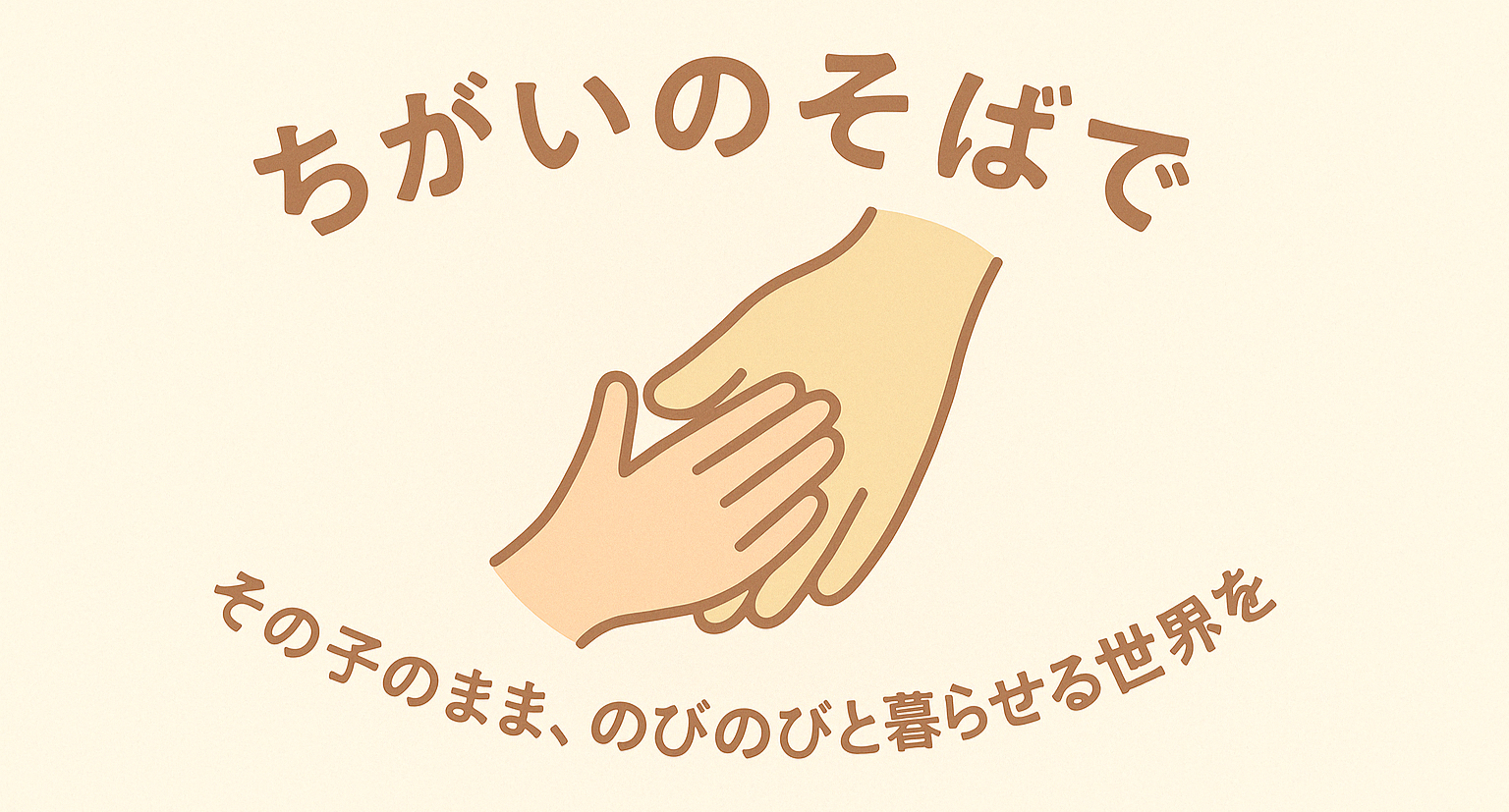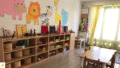医学相談という新しいステップ
子ども発達支援センターは未就学児を対象としており、
就学後は学校の発達支援コーディネーターや療育施設など、
相談の場が少しずつ変わっていきます。
そんな中、センターの先生からこう言われました。
「今後も、より専門的な立場から継続的に支援を受けたい場合は、
医療機関に相談するのが良いと思います。」
子ども発達支援センターでは、「医学相談」という制度があり、
発達障害を専門とする医師に相談できるとのこと。
これまでの記録や情報も引き継がれるというので、
ぜひお願いしたいと依頼しました。
WISC‐Ⅳの検査結果が出た後に、
その情報も参考にして年長の秋に医学相談を受けることになりました。
医学相談の流れ
当日は、約1時間ほどの面談でした。
- 事前の問診表記入
保護者が子どもの特徴や生活の様子を詳しく記入 - 情報共有
発達支援センターの先生と医師が事前に内容を共有 - 子どもとのやりとり・観察
医師が息子と話したり、遊ぶ姿を見たりしながら評価 - 保護者への質問
日常生活や困りごと、家庭での様子などをヒアリング
先生からは、問診票の内容・私や支援センターの先生からの話、
そして息子の様子を総合して、
「自閉症スペクトラム症の特徴がみられます」
と伝えられました。
普通級か、情緒級か
私はこのとき、息子を普通級にするか、情緒級にするかを迷っていました。
集団行動や推測の難しさがあり、どちらが良いのか判断に悩んでいたのです。
すると先生は、こう話してくださいました。
「知能が高く、授業自体は興味がなくても席に座っていられるタイプでしょう。
学校は“少し退屈だけど友達と楽しく過ごせる場所”になると思います。
普通級からスタートして良いのではないでしょうか。」
さらに、
「小・中学校は集団行動が多く、我慢する場面も増えるでしょう。
でも高校に入るころには、気の合う仲間と活動できるようになります。
それまでの間に“二次障害”にならないよう、無理をさせずに見守ってあげてください。」
この言葉を聞いたとき、私はほっとしました。
息子を情緒級に入れることへの不安――
「定型発達の子との関わりが減るのでは」
「大好きな実験などができなくなるのでは」
そうした心配が強かったからです。
先生の「普通級で大丈夫」という言葉は、当時の私にとって救いでした。
また、念のため「もしうまくいかなかったら…」と尋ねると、
「診断書を書いておくので、そのときはすぐに移動できます」
と心強い言葉をいただきました。
“あっさりと”下された診断と、その意味
医学相談を申し込んだのは、
医師を紹介してもらい、今後の支援をつなげていくためでした。
それなのに、初診で自閉症スペクトラム症という診断がついたことには、
正直とても驚きました。
「えっ、初診で? もう診断が下るの?」
もちろん、心のどこかでは「そうかもしれない」と思っていました。
けれど、正式に“確定診断”が出た瞬間、
どこか現実を突きつけられたような気がしたのを覚えています。
その後、「知能検査の結果と自閉症スペクトラム症の診断の両方があったから
情緒級にスムーズに移れた」と分かり、今では感謝の気持ちが大きいですが、
当時は“あっさりとついた診断”に戸惑いがありました。
診断を受けて、理解が深まったこと
診断をきっかけに、私はそれまで「発達障害全般」の本を読んでいたのをやめ、
自閉症スペクトラム症に特化した情報を学ぶようになりました。
本だけでなく、YouTubeなどでも専門家の話を聞き、
息子の行動や考え方の“理由”が少しずつ分かるようになっていきました。
「なぜこうなるのか」が分かると、
「どう支えればいいのか」も見えてくる。
診断は、そのための“出発点”になったのだと思います。
診断を伝えるむずかしさ
ただ一方で、診断を周囲に伝えることには少し勇気がいりました。
知人に「自閉症スペクトラム症なんです」と話すと、
同情されたり、急に距離を取られたりすることもありました。
近所の子が同じ小学校に通うと分かったときも、
最初は「仲良くしてね〜」と言ってくれていたのに、
診断の話をした途端に空気が変わった――そんな経験もあります。
診断を受けたことで、私自身も改めて
「息子は“発達障害のある子ども”なのだ」
と現実を受け止める段階に入ったのだと思います。
それは少し切なく、でも確かに必要な“受容のプロセス”でした。
今、振り返って思うこと
医学相談を通して感じたのは、
診断はゴールではなく、理解のはじまりだということ。
診断を受けたことで、息子の特性をより深く知ることができ、
支援の幅も広がりました。
あのときの戸惑いも、すべてが理解への一歩だったと思います。