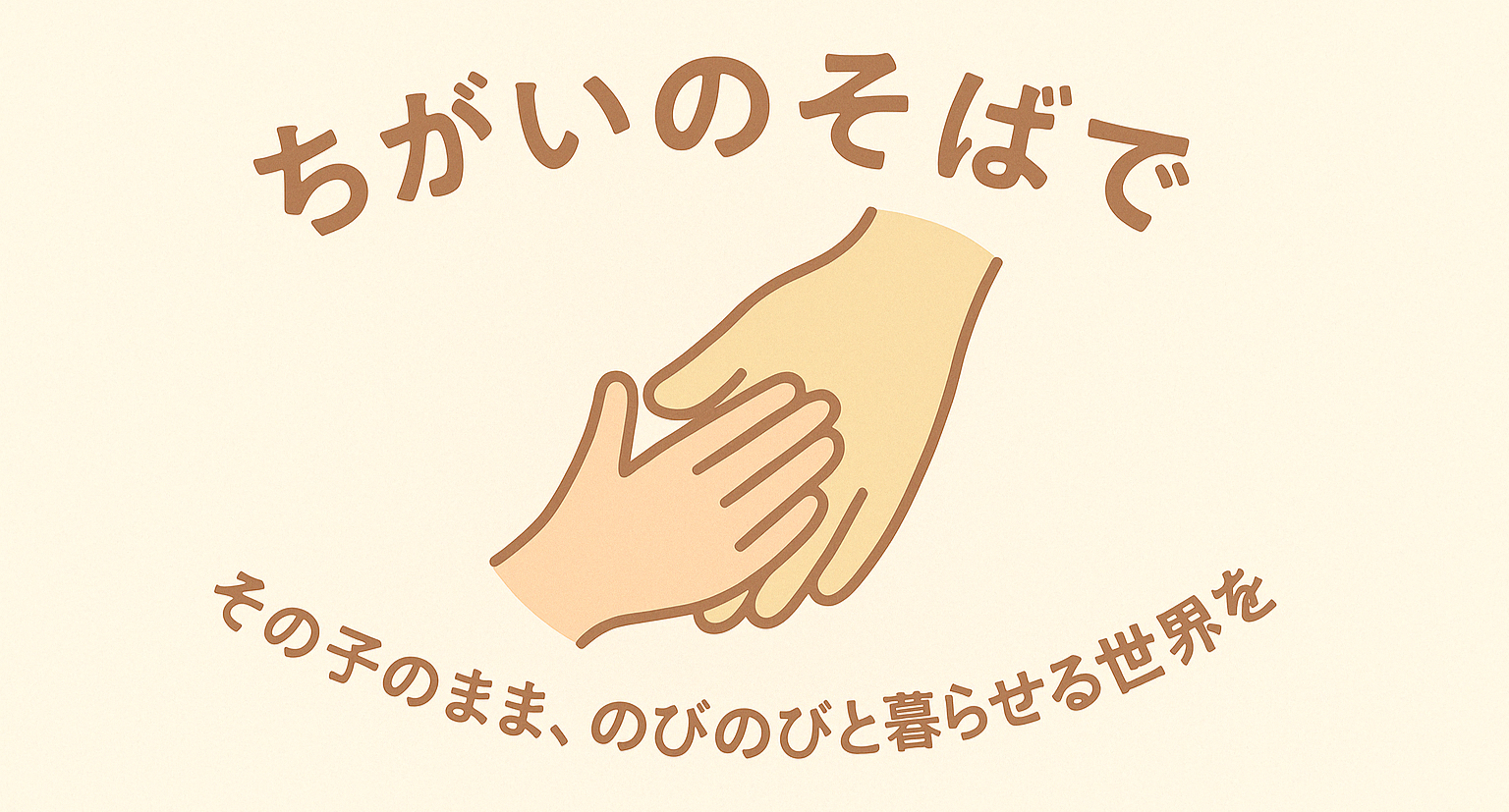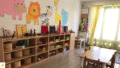支援級の仕組みを知った日
年長の春、市の就学説明会がありました。
そこで初めて、支援の仕組みについて詳しく説明を受けました。
学校には、特別支援学校のほか、普通小学校の中にも
「知的支援級」と「情緒級」という2つの支援学級があることを知りました。
通学の負担を考えると、できるだけ学区内の学校に通いたいと考えていました。
知的も情緒も異学年最大8人制で、体育や生活などの一部授業を除き、
プリントやタブレットを使った個別学習が中心になるとのことでした。
その話を聞いたとき、心の中に小さな戸惑いが生まれました。
「せっかく学校に行っても、クラスは8人だけなんだ。」
「みんなで一緒に学んだり、笑い合う時間は少ないのかもしれない。」
支援級の安心感は感じつつも、
息子にはできれば普通学級の中で、いろんな子と関わりながら学んでほしいという気持ちが強くなりました。
情緒級の見学へ
その後、知能検査の結果から
支援級に進む場合は「情緒級」に該当することが分かり、
秋に実際に見学へ行くことにしました。
見学した情緒級には、1年生の子どもが3人。
ちょうど「生活」の時間で交流級(普通級)へ行っていたため、
その間に先生からクラスの様子を詳しく伺いました。
そして、2時間目の国語の授業を見学させていただきました。
教室で見た光景
国語の時間では、3人の子どもたちがそれぞれのペースで学んでいました。
- しっかり席に座り、音読や書き取りに集中している子
- 途中で立ち歩いたり、注意がそれてしまう子
同じ1年生でも、落ち着き方や集中の仕方がまったく違っていました。
でもそれを否定する空気はなく、先生も補助の先生も、
一人ひとりに合わせて穏やかに声をかけていました。
先生が2人で子ども3人を見るという、とても手厚い環境。
一人ひとりの理解度に合わせて、
カタカナの書き方を丁寧に教えたり、分からないところを隣でサポートしたり。
確実に“できる”を積み重ねていく時間が流れていました。
また、課題が終わった子は、教室の後ろにある畳のコーナーや、
パーティションで仕切られたスペースで粘土遊びをすることもでき、
「落ち着ける場所」が用意されていることにも安心を感じました。
支援の温かさと、交流の少なさ
見学を終えたあと、私は複雑な気持ちになりました。
「この環境なら、息子も無理なく過ごせるだろうな。」
「でも、交流級の子たちと関わる時間はどうなるんだろう。」
実際、休憩時間は交流級への移動や準備の時間になっており、
普通級の子どもたちと過ごせるのは授業の一部だけでした。
友達と遊ぶ楽しさを覚えた息子にとって、
お友達との関わりが少ない環境は、きっと寂しく感じるだろうなと思いました。
見学を通して感じたことと、今の姿
情緒級は先生の目が行き届く温かい環境であり、
安心して自分のペースで学べる場所だと感じました。
一方で、当時は「普通級の子どもたちとの関わりが少なくなってしまうのでは」と不安もありました。
あっちを立てればこっちが立たない——そんな複雑な気持ちで見学を終えました。
でも、実際に息子が就学してみると、
その不安は少しずつ解けていきました。
情緒級では、先生たちが子どもの希望に寄り添いながら、
できる限り柔軟に対応してくださいます。
給食を普通級の友達と一緒に食べたり、ホームルームに参加したりすることもできます。
息子は2学期から情緒級に籍を移しましたが、
国語以外の授業やホームルーム、給食などそれ以外の活動はすべて普通級で過ごしています。
先生方が「どうすれば息子が普通級に参加できるか」を常に考えてくださり、
息子も友達との関わりを楽しみながら日々を過ごしています。
あのとき情緒級を見学して感じた不安も、
実際に通ってみると“現場の柔軟さ”に救われました。
支援と交流のどちらも大切にしてくれる先生方に、
今は心から感謝しています。