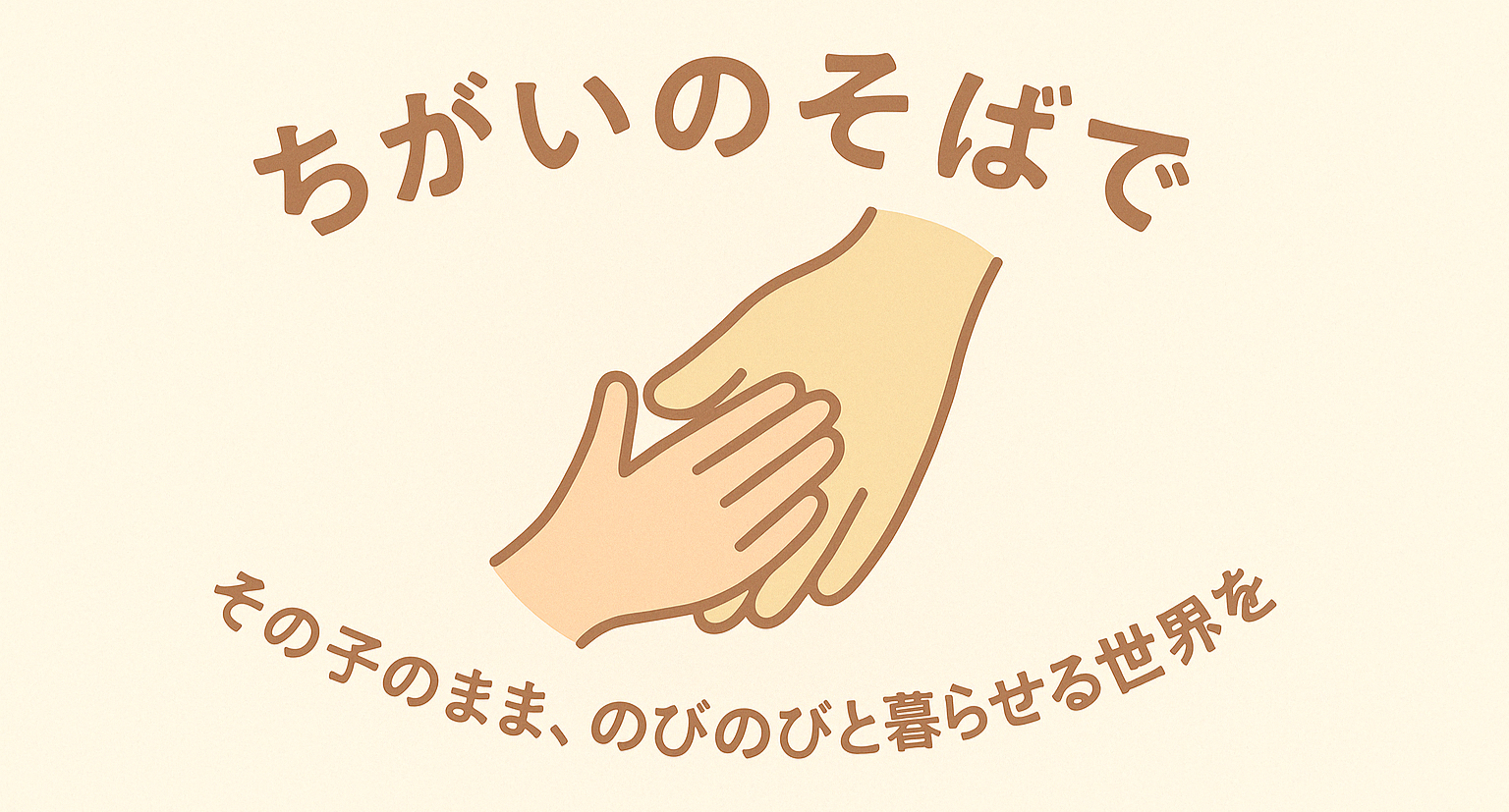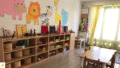はじめての知能検査
年長の春、こども発達支援センターで「WISC‐Ⅳ(ウィスク)」という発達検査を受けることになりました。
年長にならないと実施できない検査で、以前から「年長になったら行いましょう」と言われていました。
この検査は、子どもの特性をより深く理解するためだけでなく、
小学校で支援級(知的支援級/情緒級)を検討する際にも必要なデータになります。
当時の私は、息子が文字を読めず書けず、集団行動も苦手だったため、
「理解力が低いのではないか」「境界知能かもしれない」とずっと不安を抱いていました。
検査当日の様子
先生からは、「できるだけ良いコンディションで受けましょう」と言われ、
午前中の疲れていない時間に実施することに。
前日は「明日はテストだから早く寝ようね」、
当日も「頑張ってね!」と家族みんなに声をかけてもらい、
息子もその期待に応えるように、これまでにない集中力で臨んだそうです。
驚きの結果
結果を聞いたのは、1か月後。
全検査IQは122。
先生も私も思わず顔を見合わせて「えっ…?」と驚いてしまいました。
これまで「理解が追いつかないのでは」と思っていたのに、
むしろ知能は高いほうだったのです。
詳しく見ると、
- 言語理解・知覚推理・ワーキングメモリ:120前後
- 処理速度:94
と、得意・不得意の差がとても大きい結果でした。
この“凹凸の大きさ”こそが、日常生活での困りごとを生みやすくしている、
と先生は説明してくださいました。
大きな衝撃と気づき
私はこの結果に大きな衝撃を受けました。
ずっと「境界知能かもしれない」「できなくても仕方ない」と思い込んでいたのに、
本当は息子の中に、強い知的な力があった。
「できないのではなく、やり方が合っていなかっただけかもしれない。」
そう気づいた瞬間、涙が出るほど反省しました。
たとえば、処理速度が低いことがわかったことで、
手先の不器用さから文字を書くことに時間がかかっていたと理解できました。
「書けない=覚えられない」と思い込んでドリルを繰り返しやらせていたのは、
私のやり方がいけなかったのだと思いました。
学び方を変えてみた
そこで、発想を切り替えてみました。
文字を書くことにこだわらず、ひらがな・カタカナカードでゲーム感覚の学習に変更。
「これ、なーんだ?」
「あ!“れ”だ!」
そんなやりとりをしながら遊ぶうちに、
あっという間に文字を覚えてしまったのです。
驚きと同時に、「この子は、知能がちゃんとある」と感じました。
書くことが苦手でも、考える力は強い。
そう理解してからは、“書かせる”より“考えさせる”学び方にシフトしていきました。
息子を「信じる」ようになれた
検査の結果が変えたのは、息子への関わり方だけではありません。
私自身の心のあり方も変わりました。
それまでの私は、
「どうせできない」「無理をさせたくない」
という気持ちから、どこかであきらめていた部分がありました。
でも今は、
「この子には、できる力がある」
「苦手なことも、工夫すれば乗り越えられる」
そう信じて、息子のペースで挑戦を支えられるようになりました。
「手が不器用だけど、考えることは得意だよ」
そう伝えられるようになったことで、
息子の自己肯定感も少しずつ上がっていったように思います。
検査がつないでくれた次の一歩
この検査結果は、後に息子が小学校で情緒級へ籍を移すときにも役立ちました。
教室での困りごとが出てきた際、結果をもとにスムーズに支援へとつなげられたのです。
あのとき検査を受けていなかったら、
息子の特性を「理解力の問題」と誤解したままだったかもしれません。
そして今、思うこと
発達検査は、決して“できる・できない”を測るためのものではなく、
「どうすればその子が力を発揮できるのか」
を見つけるための地図のようなもの。
検査を受けたことで、私は息子を“評価”するのではなく、
“信じる”という関わり方に変わりました。
そして今も、このとき得た気づきが、
私の子育ての軸になっています。