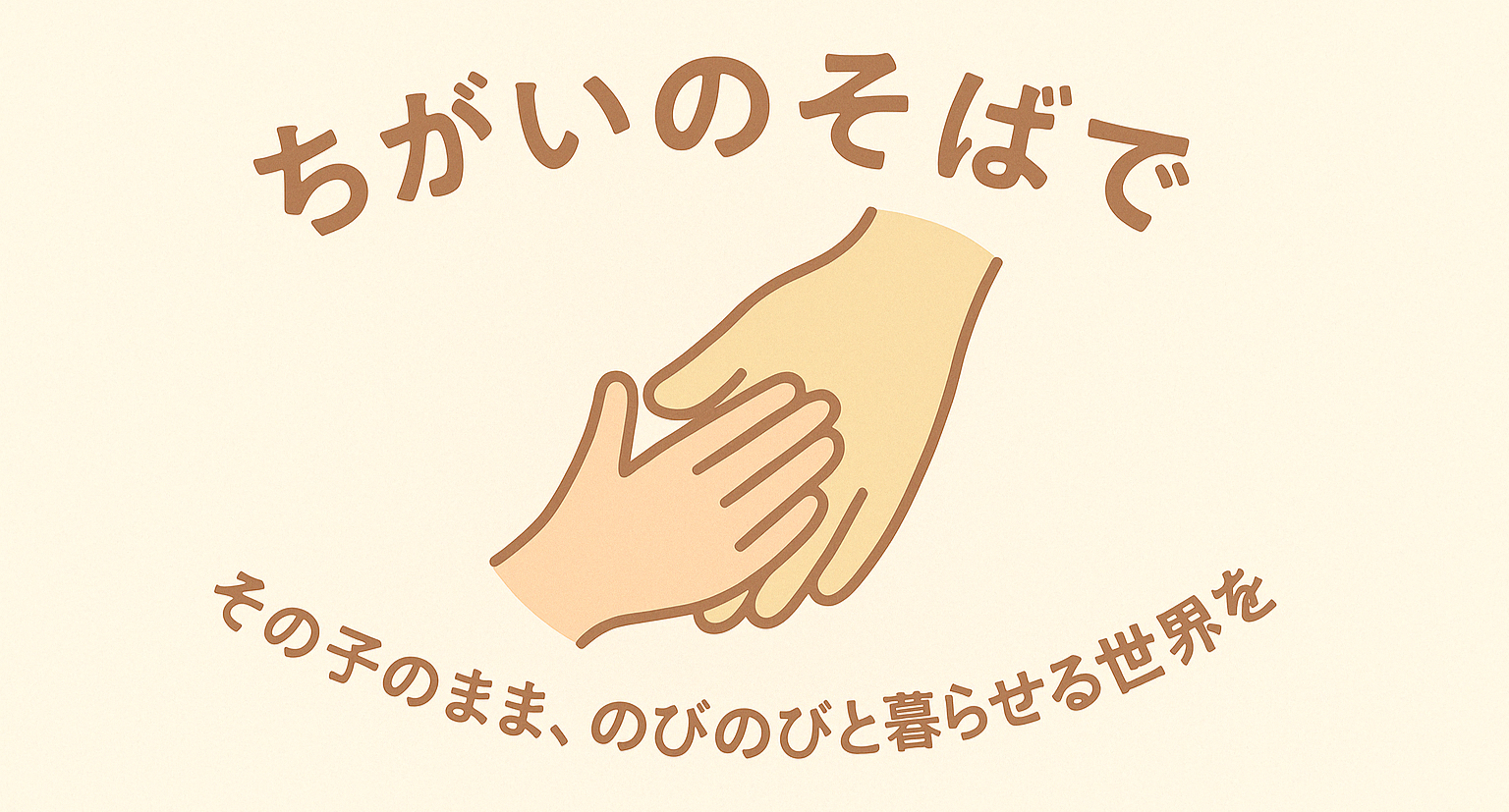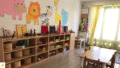「連絡票」とは?
就学を前に作成する「引継ぎのための連絡票」は、
子供が入学後も安心して学校生活を送るために、家庭・園・療育機関が連携して作成する書類です。
保護者が家庭で感じている特性やサポートの工夫、
保育園や療育での取り組みや配慮をまとめ、
学校に“これまでの歩み”を引き継ぐための大切な橋渡しの書類となります。
この連絡票をもとに、小学校では個別の支援計画が立てられ、
その計画は中学校卒業まで引き継がれていきます。
連絡票の作成を依頼
私は、
- 子ども発達支援センター
- 通っていた保育園
の2か所に連絡票の作成をお願いしました。
書面をそのまま学校へ郵送することもできましたが、
せっかくなら「直接、息子のことを丁寧に伝えたい」と思い、
学校への面談を依頼しました。
その面談を2月にお願いし、3月上旬に実施しました。
面談の準備と工夫
面談の担当は教頭先生でしたが、
より専門的な視点から話ができるよう、
発達支援コーディネーターの先生にも同席をお願いしました。
この判断は、今振り返ると本当に良かったと思います。
というのも、4月には人事異動があり、教頭先生が新しい方に変わったのです。
4月以降、環境調整のために色々な相談を学校としていくことになったのですが、
その際に発達支援コーディネーターの先生と事前に顔合わせをしていたため、
スムーズに相談することができました。
面談では私が連絡票を読み上げながら、
それぞれの項目に対して具体的なエピソードを補足し、
学校側にも息子の姿をイメージしてもらえるように伝えました。
発達支援コーディネーターの先生は自閉症スペクトラム症に詳しく、
「しっかり伝わった」と感じられる時間でした。
実際の連絡票に書かれていた内容
実際にどんな内容が書かれていたかを紹介します。
現在の状況
- マイペースな傾向があり、身の回りのことや周囲の状況への興味・理解には弱さが見られる。
- 初めてのことや慣れないことに取り組む際は、理解や行動に時間がかかる。
- 聴覚よりも視覚の理解が得意で、見て把握する方が理解しやすい。
- 1対1では集中して話を聞くことができるが、集団の中では注目が散りやすく、一斉指示を一度で理解するのが難しい場合がある。
- 自分の気持ちや要求を言葉で表現することが苦手で、分からないときは机にうなだれるなど、態度で示すことがある。
- 視覚的な刺激に注意が向きやすい一方で、やるべきことから気が逸れてしまうことがある。
- 興味のない事柄の理解が苦手で、日常の中でも情報をつかみにくい場面がある。
- 読み書きは年齢相応の力があるが、本人にとっては負担が大きく、苦手意識がある。
支援内容・引継ぎ事項
- 視覚的な支援が有効。
話を聞き続けることは難しいため、絵や文字などの視覚情報を併用すると集中して聞くことができる。 - 座席の位置に配慮を。
教員の指示が入りやすく、目が届きやすい場所が望ましい。 - 全体指示後の確認を。
一斉指示のあと、理解できたかどうか個別に軽く確認してもらえると助かる。 - 個別の声かけが効果的。
やるべきことが分からず戸惑っている様子が見られたときは、短い言葉で個別に声をかけると安心して行動に移れる。 - 達成時の肯定的な声かけを。
読み書きへの苦手意識があるため、できたときに具体的に褒めてもらうことで意欲が高まる。
このように、連絡票では「どうすればできるようになるか」「どんな支援が効果的か」という視点でまとめてもらえました。
先生方が息子の特性を理解し、環境を整えるうえでの具体的なヒントが書かれていて、とても心強く感じました。
面談を終えて感じたこと
面談を通して、学校側が「どんな配慮が必要か」だけでなく「どんな支え方がその子の力を引き出すか」という視点を持ってくださっていることが伝わりました。
そして、
「担任の先生にもきちんと引き継ぎますね。」
という言葉に、とても安心しました。